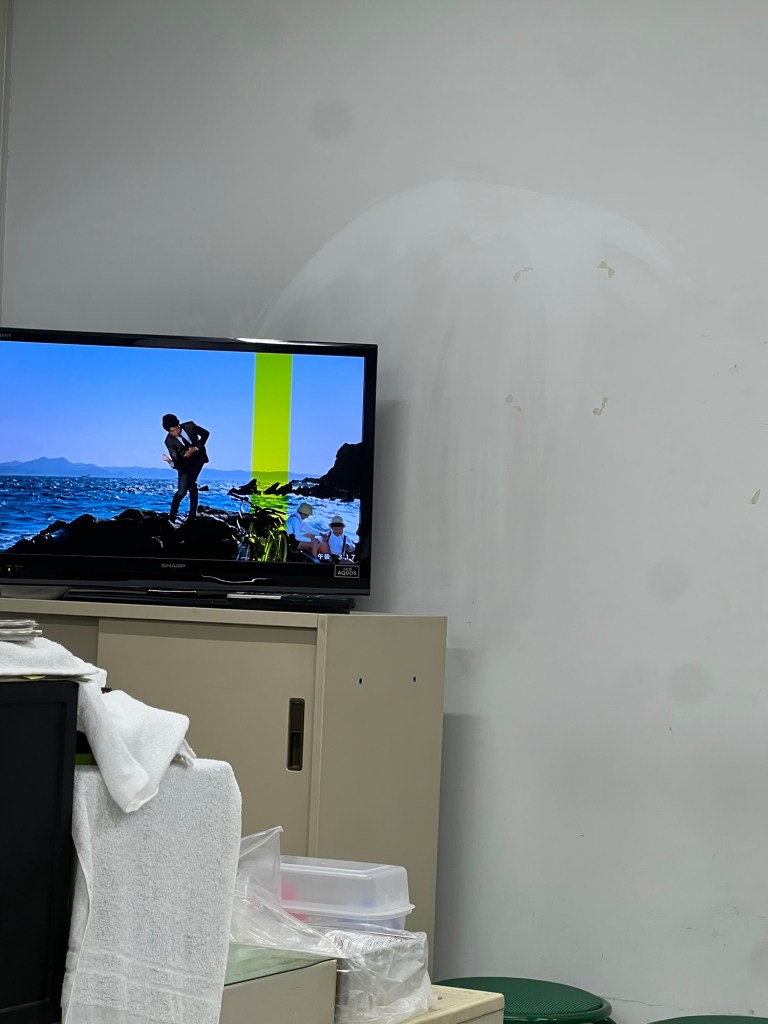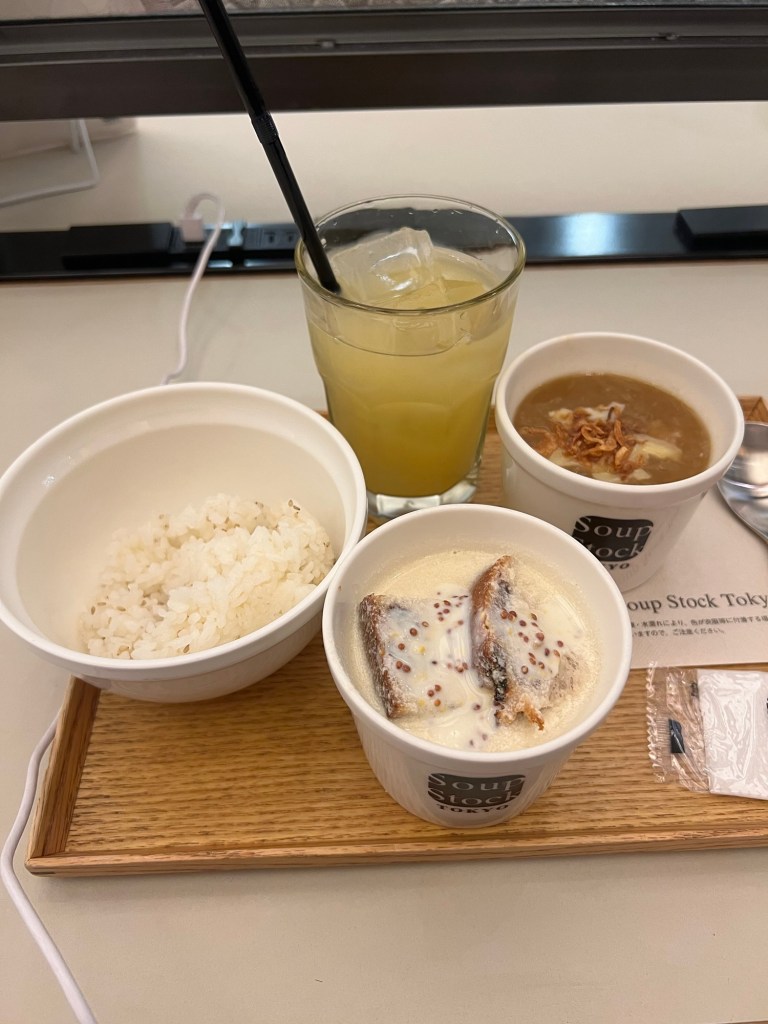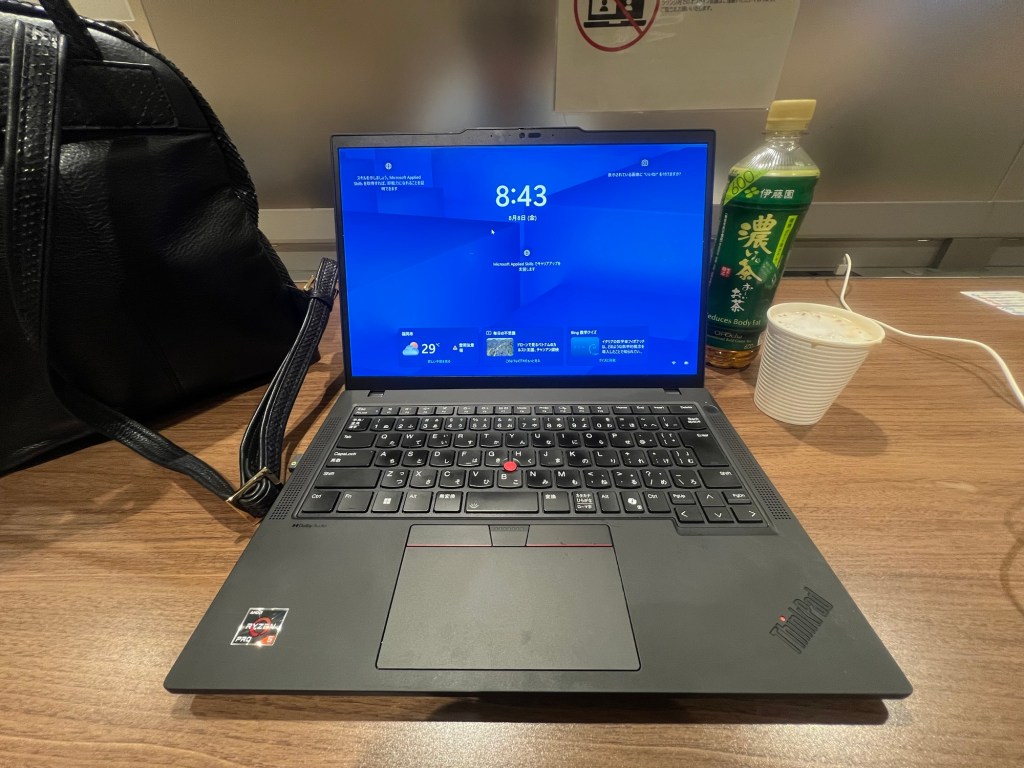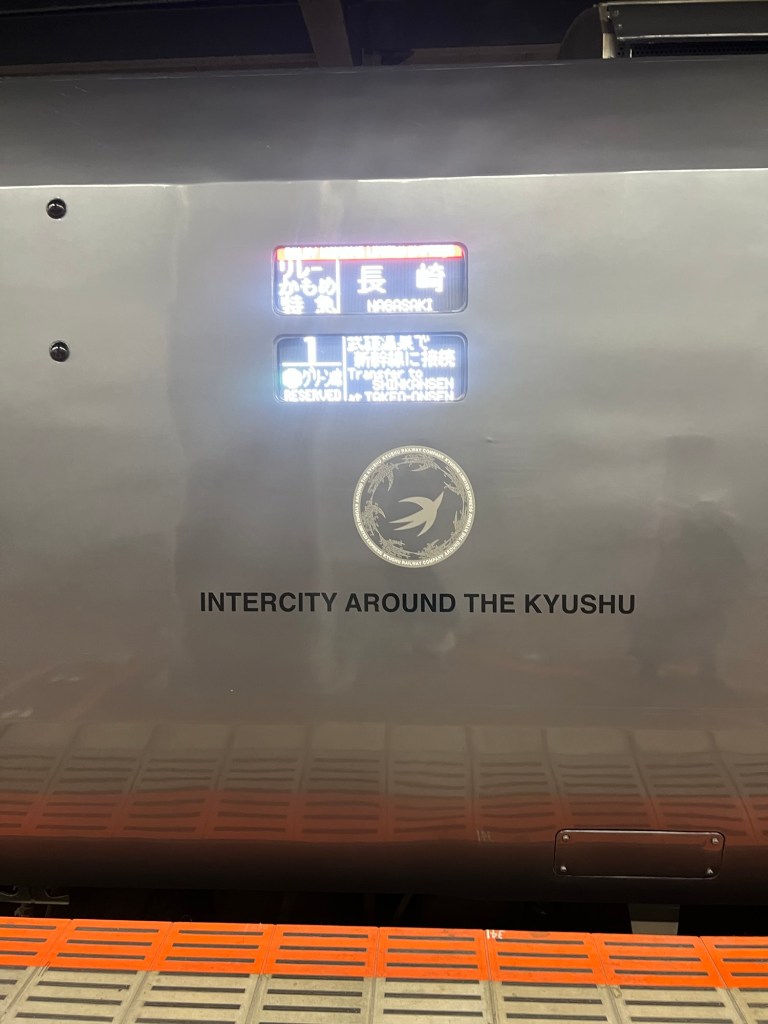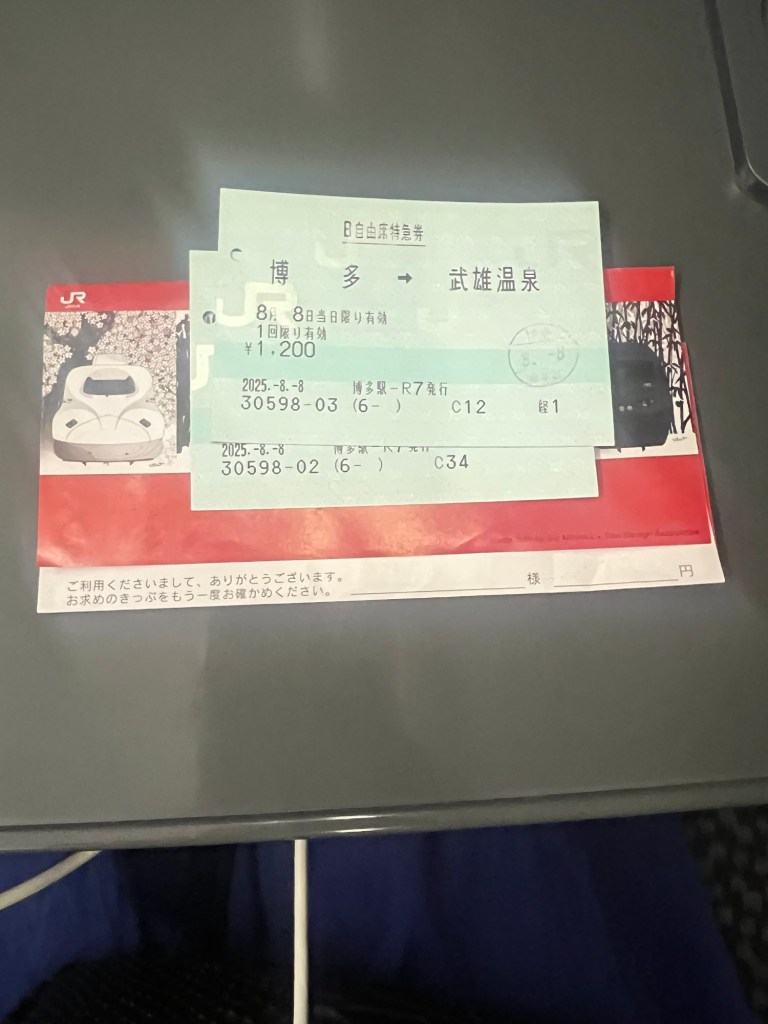——そして私は、まだ彼を嫌いになれない。
錦糸町の夜は、いつだって人の心に正直だ。
飲み会の帰り道、冷えたアスファルトを踏みしめながら、
私は古谷(仮名)のことばかり考えていた。
既読の重さ。
軽すぎるスタンプ。
“他の誰にでも送っていそうな笑顔”。
それでも彼のことを考える自分がいる。
気持ちが残っている——
そんなこと、自分が一番よく分かっていた。
背後から名前を呼ばれたとき、
振り返らなければよかったと思う。
「ひとつ言っとくわ」
そう前置きしたのは、石原(仮名)。
いつも無表情で、
人の懐に静かに入ってくるタイプの男。
「古谷、結婚してるよ。前から」
その一言で、
胸の奥に隠していた温度が、音もなく崩れた。
“知りたくなかった”
そのほうが、正しかったかもしれない。
だって私は、
彼にいまだに気持ちがあるのだから。
馬鹿みたいでしょ?
裏切られた側なのに、まだ情が残っている。
でも、恋なんてそんなもの。
論理じゃなく、脈拍で動いている。
彼の言葉を思い返す。
仕事の話をするたびに見せた、あの柔らかな目。
誕生日にくれたプレゼント。
夜遅くまで続いたメッセージ。
あれは、全部何だったの?
なんで、あんなに優しかったの?
まだ知りたい自分がいる。
まだ信じたい自分がいる。
その“まだ”が、女を苦しめる。
部屋に戻ると、
古谷からスタンプが届いていた。
軽いハイタッチ。
いつもの距離感。
いつもの建前。
本当はもっと話したい。
もっと聞きたい。
もっと、彼の本音に触れたい。
——そんな気持ちを、
私はスマホの光の中に押し込めた。
私は強い女のふりをするのが得意だ。
でも本当は、
まだ彼が好きだった。
だからこそ、悔しい。
だからこそ、泣けない。
嘘をついた男は軽いけれど、
その嘘に傷つく女はいつも重い。
石原は言った。
「知らなかったの、お前だけだよ」
その言葉が胸に刺さる。
本当の裏切りは、嘘ではなく “蚊帳の外に置かれた事実” かもしれない。
私だけが知らされず、
私だけが信じていた。
それでも、まだ彼を切れない。
まだ、古谷の名前を消せない。
——けれど私は決めた。
私は古いページにしがみつく女にはならない。
嘘の値段は、彼自身に払ってもらう。
私は私の未来に投資する。
彼がどういう立場であれ、
どういう事情を抱えていようが、
それは彼の問題。
私の涙は、
誰かの嘘のためには流さない。
ただひとつ、胸にだけしまっておく。
“いまでも、ほんの少しだけ、あなたが好きだった。”
それだけで十分だ。
それだけで、私は前に進める。
錦糸町の街灯は、
まるで私の気持ちを知っているかのように滲んで見えた。先日高校の同級生に話を聞いてもらった餃子ナイト🥟


今日も副業先で朝ごはん🥞