週が明けた月曜の朝。
職場はいつもより静かだった。
電話の呼び出し音も、雑談も、
どこか遠慮がちで、耳にまとわりつくような沈黙があった。
表面上は変わらぬ日常を装いながらも、
空気だけがぴりついていた。
その理由は、誰もがうすうす分かっていた。
先週の会議室の出来事。
そして、その裏にある“通報”という存在。
直接的な言葉で言う者はいない。
だが、視線が少しずつ動き出す。
一部の社員は、まるで偶然を装うように私のデスク前を通り、
中にはやけに親しげに話しかけてくる者もいた。
「最近、ちょっと空気おかしいよね」
「なんか、裏で動いてるのかな」
「誰が言ったんだろうね…まあ、営業の数字に絡んだ話みたいだけど」
言葉の端々に、“詮索”という毒が混じっていた。
まるで誰かを名指しするために、
“会話”という皮をかぶった刃物で、周囲をじわじわ切り裂いているようだった。
三田の姿も、変わりはなかった。
明るめのベージュジャケットに、揺れるイヤリング。
いつも通りの営業スタイルで出社し、
顧客への架電も、社内チャットも、平常運転だった。
彼女が、まるで何もなかったかのように業務をこなすその姿に、
ある者は「肝が据わってる」と言い、
ある者は「若いって怖いね」とつぶやいた。
でも誰も、問題の本質には触れようとしなかった。
“なぜ起きたのか”ではなく、
“誰が言ったのか”ばかりを探っていた。
沈黙のなかで、私はただ一人、何も語らずにいた。
それが、“私ではない”というアリバイになるわけでもないことは知っている。
けれど、何を語らないかを選ぶことで、
この会社の“品位”を映す鏡になるとも思っていた。
私は、噂にも、視線にも、巻き込まれない。
黒革の手帖に記録された“事実”の重みだけを、黙って受け止めている。
通報制度とは、本来、告発者を守るためにあるはずだった。
だが、ここでは逆だ。
声を上げた者こそ、詮索され、距離を置かれ、やがて孤立する。
それを誰もが知っているからこそ、
誰も声を上げず、誰も正さず、
「誰が言ったのか」だけが、正義の代わりになる。
誰かの正義を求めているふりをしながら、
本当は“面倒な真実”から目を逸らしているだけ。
私はそれを、「正義の副作用」と呼んでいる。
噂が私の耳元をかすめるたびに、
私は静かに、黒革の手帖を閉じた。
語る必要のないことは、語らない。
でも、記す必要のあることは、忘れない。
最近1番美味しいと感じた飲み物
シロップ少なめミルクコーヒー スターバックス💚
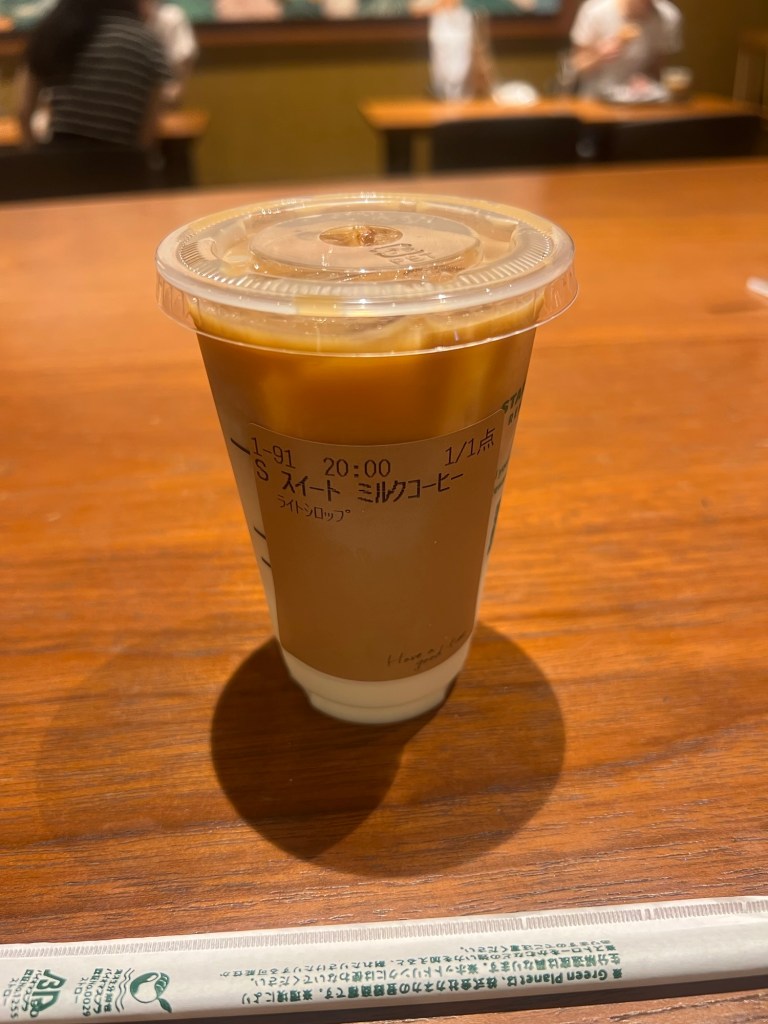

コメントを残す