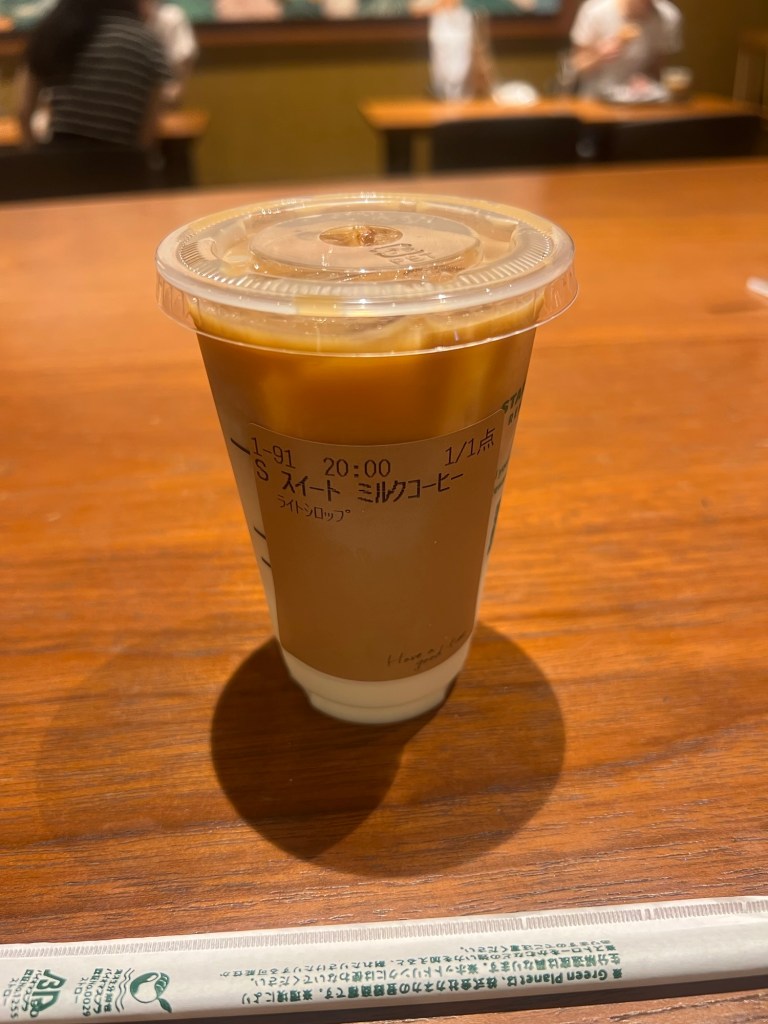「証拠がないなら、事件じゃない」
そう言い切ったのは、警察官だったか、それとも私の中の“冷静さ”だったのか。
手首に残る青痕、腹の裂傷、両腕両肘、両足首の怪我と、胸に残る違和感だけが、あの夜を語っている。
⸻
連れてこられたあの建物の前――
鉄の扉が閉まるよりも前に、私は叫び続けた。
「冷静に話せる人を、出してください」
「話のわかる人を呼んでください」
「私は酔っていません。不当です」
「鍵が盗まれた。家に誰かが入ってしまう」
同じ言葉を、50回ほど。
低く、そして大きく。
感情に任せるのではなく、冷たく、届くべき相手に向けて発した。
必死ではなく、計算された抗議として。
その執拗さが効いたのか、ようやくひとりの男が姿を見せた。
私服姿の、少し疲れたような顔の警官。
名をカワナミと言った。
黒いウィンドブレーカーを着てこちらに歩いてくるその男に、私はまっすぐ目を向け、理路整然と話した。
「私は酔っていません。暴れてもいません」
「このままでは家に誰かが侵入します。危険です」
「帰宅させてください。私は、ただ守りたいだけです」
彼の目が一瞬揺れた。
正論は届いていた。
でも、“届く”ことと“通る”ことは、別だった。
カワナミはもうみんな帰ったと思うけど、わかる人を探してくると言った。
「……反省したか?」
割って入ったのは、Yという名の制服警官。
あの薄く笑った口元。目元は、白夜行というドラマで見た武田鉄矢の警察の目。
まるで私が、何か悪意のある“芝居”を演じていたとでも言うような口調だった。
そして、決定的な一言を投げつけてきた。
「酔ってないことも、反省してることも証明できないなら……帰せないよ」
この国では、女が“正気”を名乗るにも、証明が必要らしい。
冷静であろうとした私に突きつけられたのは、理不尽の極みだった。
私はその場で、静かに頭を下げた。
「……帰してください」
それだけ。
媚びも、涙も添えず。
ただ、冷静に、確実に。
家と自分自身を守るために。
屈したわけじゃない。
ただ、戦う場所を変えただけだ。
この社会で生きる女には、それしか選択肢がないこともある。
⸻
6時間。
午前2時11分――
私はようやく、“釈放”という名の解放を告げられた。
手渡されたのは、取り上げられていた私物のすべて。
……“すべて”のはずだった。
でも、白い厚底のサンダルだけがなかった。
記憶の中では、確かにあの中華料理屋の前で、足元から引き剝がされた。
名も知らぬ制服たち――いや、名前は覚えている。山野と佐原。
彼らの手によって、私は人である前に「物」として扱われた。
外は、大雨だった。
どこまでも無関心な天気。
濡れたアスファルトを踏む音が、私の心に張られた糸を静かに軋ませる。
6時間、水も口にしていなかった。
喉はからからだった。寒かったのでトイレに行きたいと主張したが扉は開けてもらえなかった。放り込まれたブランケットに用を足すしかなかった。
飢えではなく、乾いた怒りが、体の芯に溜まっていた。
私は裸足のまま、署の隣にあったローソンに入った。
深夜の冷えた店内。
棚のいちばん下に並んでいた1リットルのポカリスエットを、何も考えずに手に取った。
買うことが「自由」の証明に思えた。
足元を見られてもかまわなかった。
見られて、何になる。
私はこの夜のすべてを記憶している。
忘れない。
許さない。
でも、見下されても、屈しない女でいることだけは、私の選んだ復讐だった。
私は納得がいかなかった。
鍵が犯人から返されていない。
あれだけの暴力と横暴を振るわれた末に、私はまだ「加害されたまま」だった。
だから私は、ローソンを出た足でもう一度、警察署に戻った。
1階の窓口で、YとSを呼ぶように伝えた。
応対に出てきたのは、S。
あの中華料理屋の前で、私の身体をパトカーに押し込んだ男だ。
能天気な顔で、彼は言った。
「えっ、なんで。さっきはそんな物も持ってなかったよね?」
彼が指差したのは、私の右手に握られた1リットルのポカリスエットだった。
私はその視線から、彼の“認識”を即座に読み取った。
彼にとって、私はただの「酔った女」だったのだ。
「6時間以上、何も飲んでないですよ?」
私が静かに返すと、Sは一拍置いて「えっ」とだけつぶやいた。
その顔に、かすかな戸惑いが滲んでいた。
自分が、何も見ていなかったことへの気付き――
あるいは、それを認めざるを得ない“気まずさ”。
私は淡々と言った。
「靴がありません。すぐに、中華料理屋の前を確認してください」
Sは何も言わず、うなずいた。
私もパトカーに乗り込み、現場へ向かう。
道中の会話はなかった。
その無言が、何より雄弁だった。
中華料理屋の前に到着すると――
そこに、白い厚底のサンダルが、きちんと揃えて置かれていた。
雨に打たれ、ずぶ濡れで、真っ黒になって。
だが、左右ぴたりと揃えられたその姿は、
まるで誰かがわざと丁寧に並べたようにも見えた。
まるで、「証拠はあるが、お前のものにはしない」とでも言うように。
私は黙ってそのサンダルを拾った。
汚れても、濡れても、これは私の足で歩いてきた証だった。
思い返せば、1度目に警察署を出たとき――
YもSも、ただぽかんと口を開けたまま、言葉ひとつ発さず私を見送った。
私が濡れながら裸足でローソンへ向かっても、誰も何も言わなかった。
それが、この社会の「無関心」という名の態度。
だが、2度目の出発のときは違っていた。
Yが、無言でボロボロのビニール傘を差し出してきた。
取っ手の部分は曲がり、骨も歪んでいた。
雨の中、それはまるで**“これは気遣いだ”とでも言いたげなアリバイのような傘**だった。
私は黙って受け取った。
礼も、拒絶も、しなかった。
その傘が濡れていようと、
破れていようと、
それでも私は、自分の足で帰るしかなかった。
私はその場で、Yに言った。
「鍵も探してください。まだ見つかっていません」
Yは無言で頷いた。
そして、片手に懐中電灯を持ち、歩道脇の植え込みを軽く照らした。
ほんの5秒ほど。
探しているというより、探す“ポーズ”に近かった。
それから顔を上げ、まるで芝居の幕引きのように言った。
「……ないですね」
そのまま、Sとふたりでパトカーに戻っていった。
まるでこれで一件落着とでも言うように。
私は、一人で探し続けた。
歩道、側溝、植え込み――
濡れたアスファルトに膝をついてもかまわなかった。
でも、埒が明かなかった。
私はパトカーの方へ歩き、窓をノックした。
中に、自分のカバンが見えたのだ。
「中に私のカバンがあります。返してください」
そう伝えると、助手席にいたSが驚いたように振り返った。
「えっ……? あ、置いてあるの気づかなかった」
あの夜、どれだけのことが「見落とされていた」のか。
それが、意図的なのか、無関心なのか――
どちらにせよ、私にとっては同じことだった。
Sはカバンを手渡しながら、言った。
「ほら、あそこにタクシーもいるし。もう帰りなさい」
言葉の端に、**“これ以上関わりたくない”**という本音が滲んでいた。
彼らにとっては、私は“処理が終わった案件”だった。
でも私にとっては、まだ何も終わっていなかった。
タクシーに乗り込み。家まで1万円程度かかった。
タクシー運転手のおじさんは、本当に今日は酷いことされましたねと、話を親身に聞いてくれて優しかった。
家に着いたが鍵がないのでオートロックに入れない。そう心配していたが、タクシーで家の近くに到着すると、ラッキーなことに目の前を同じマンションの20代女性が歩いていたので、後ろからついていき、マンション玄関は突破。その後鍵屋に連絡して夜中だが40分で来てくれた。
そこで提示された見積もりはなんと4万2000円。
私はかぎやの30代の男性に事情を話し、目を瞑った。すると今回は特別に、、、と、2万7000円まで、負けてくれた。作業が始まって30分で家に入れたが、もう、明け方でバイトが入っていたので、眠る暇はない。体全体がひどく痛んでいたが今回のことを警察署のご意見係や他の警察署などに連絡するのを急いだ。
作業は30分ほどで終わり、私はようやく部屋に戻れた。
すでに空が白み始めていた。
体中が痛み、睡眠は叶わなかった。
けれど、そのままバイトに向かう準備を始めた。
★同時に、マンションの管理会社にも電話をかけ、鍵が盗難にあったことを伝えた。
★留守番電話に切り替わったため、「至急ご連絡いただきたい」とメッセージも残した。
★その声にも、もう怒りはなかった。ただ、冷たく、事実だけを伝えた。
ベッドにもたれながら、私は携帯を開き、指を動かし始める。
警察署のご意見係 別の署の通報窓口 相談フォーム
抗議の言葉を連ねる手に、迷いはなかった。
痛みも、疲れも、眠気も、
「私が悪くない」と知っているからこそ、消化されていく。
腹の裂傷が痒く痛んだ。


普通の人が経験しないようなことばかりしてると、向上心が人一倍強くなる。
5000円分のAmazonギフト券もらって、無料トライアルできるようなので、知識と向上心を読者の方にもをお裾分け。

、